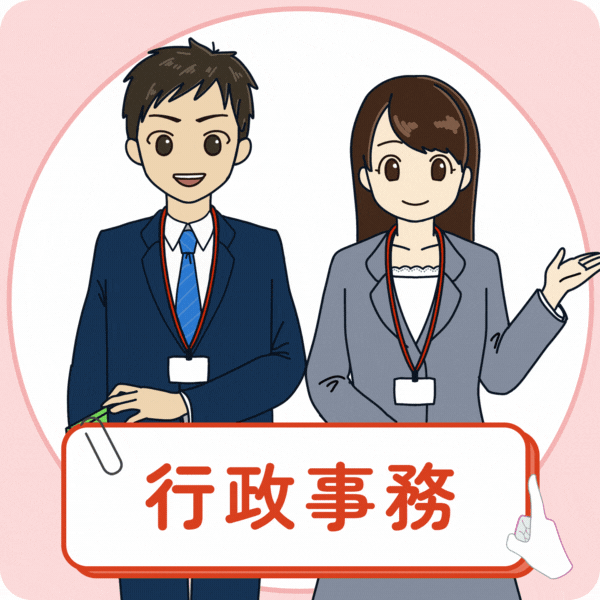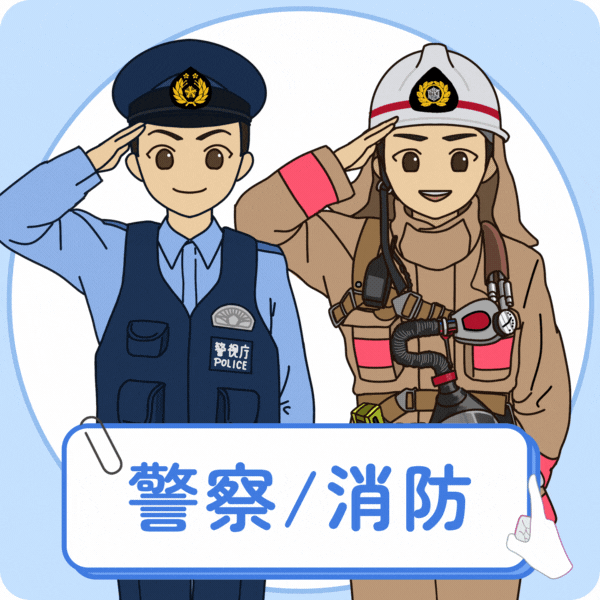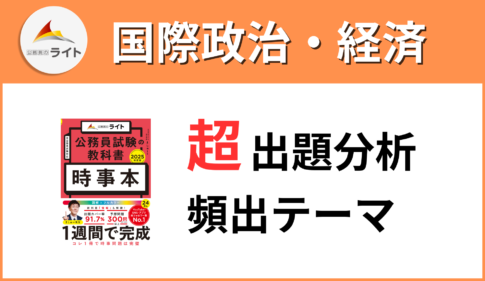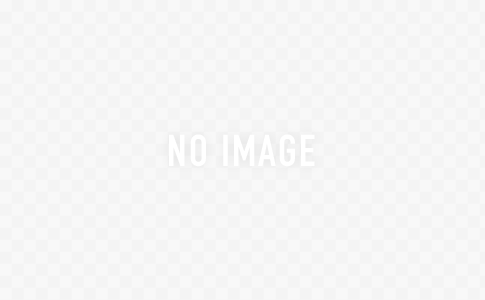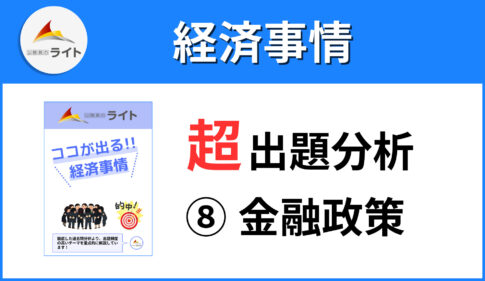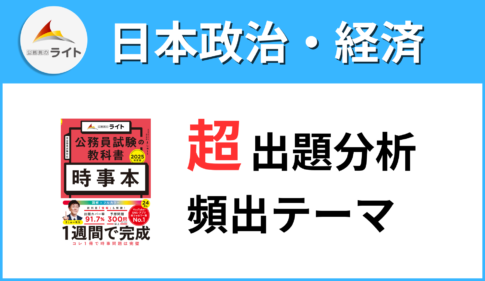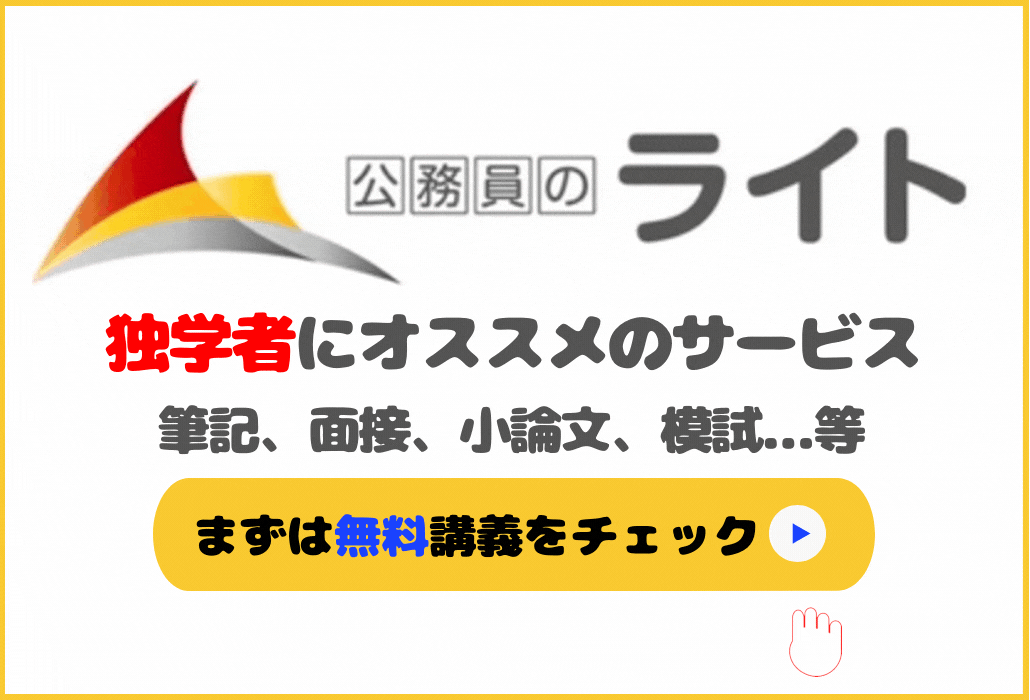こんにちは😊公務員のライトです!
Follow @koumuinright7
今回は、【公務員試験の最新時事:食品ロス】について、ポイントを解説していきます。
目次
【公務員試験の最新時事】食品ロスとは
はじめに
皆さんは、食品ロスということばを聞いたことがありますか?日本では、スーパーや外食等で、まちを歩けばいつでも食品を手に入れることができるので、とても恵まれている環境であるといえます。しかし、その恵まれた環境に甘えてしまうことで食品ロスが発生してしまいます。ここでは、食品ロスについて知り、今後の暮らし方を見直すきっかとしてみてください。
食品ロスの定義
食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。食品ロスは事業活動に伴って発生する「事業系食品ロス」と、各家庭から発生する「家庭系食品ロス」の2種類に分けられます。
食品ロスと食品廃棄物の違い
食品ロスと食品廃棄物は同じように使われる言葉ですが、実際には定義は大きく異なります。食品ロスとは「まだ食べられるのに捨てられる食品」のことです。飲食店での食べ残しや、スーパーやコンビニの賞味期限切れ商品が食品ロスにあたります。一方、食品廃棄物とは捨てられた食べ物全般を指し、野菜の皮や種、魚の骨など一般的には食べない部分も含みます。

【公務員試験の最新時事】日本の食品ロスの現状

(出典:農林水産省HP)
日本での食品ロスの量は減少傾向で、2020年度は年間522万トン(推計値)です。具体的なイメージで表すと、1人当たり年間約41kgの食品を無駄にしてしまっている現状です。これは1人が毎日お茶碗1杯程度のご飯を捨てているのと同様です。この現状から、日本は食品ロス量の目標として、「2000年度比で2030年度までに半減させる」としています。
【公務員試験の最新時事】日本の食品ロスと食料自給率
令和3年度の日本における食料自給率は38%で低い値となっています。日本の食糧は海外からの輸入に大きく依存していますが、大量の食品ロスが発生しています。他方、世界的な人口急増が要因となり、地域によっては深刻な飢餓や栄養量の問題が発生しています。そのため、SDGsにおいても食品ロスの削減が重要な課題となっています。
【公務員試験の最新時事】SDGsと食品ロスの関係
SDGsの目標12「つくる責任・つかう責任」の中に「2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させる。」というターゲットがあります。また、食品ロスの原因や改善のための取組には多くのSDGsの目標が関係しています。
【公務員試験の最新時事】食品ロスの発生要因
食品ロスは、企業と家庭両方から発生しますが、それぞれ要因が違います。ここでは、その要因の一部をみていきましょう。
食品ロス発生要因:企業
外観品質基
外観品質基準とは、その名の通り見た目の基準を意味します。基準に満たない食品は規格外として扱われ、飼料化・肥料化されたり、廃棄処分されたりします。例えば、あるクッキーがあり、少し焦げ目の色が濃いものや、ほんの少し割れたもの、数ミリ大きかったり、小さかったりするものも規格外となります。
規格外
製造のひとつ前の過程、農業や畜産でも規格外の食品ロスは発生します。例えばあるきゅうりがあるとします。本来キュウリは曲がる性質でありながら、梱包や運搬の都合によりまっすぐに育つように品種改良が繰り返され、それでも生産過程で発生する曲がったキュウリは規格外として扱われます。

食品ロス発生要因:家庭
過剰除去
家庭から出る食品ロスで最も多いのが「野菜類」、次に多いのが「果実類」です。皮や種の周りを厚く剥いたり、古くなった部分を切り落とすなど、食べ残しのほかに調理過程で出る食品ロスが過剰除去です。例えば、白菜の黒い斑点は、食べても問題ありませんが、見た目の違和感から捨ててしまう方もいます。
食べ残し
これは、言葉通り出された食品を苦手等の理由からすべて食べずに残すことで食品ロスになっています。
直接廃棄
賞味・消費期限切れにより、手をつけずに食品を捨てることを直接廃棄といいます。食品の買いすぎや冷蔵庫内の管理不足が原因となり、食品の直接廃棄につながります。

【公務員試験の最新時事】食品ロスの問題点
食品ロスによって、日本だけではなく地球規模の問題に発展するといわれています。具体的な問題点を以下でみていきましょう。
地球温暖化と環境破壊
食品ロスは地球温暖化の原因でもある温室効果ガスの排出に関係しています。食品廃棄物を埋め立て処理する際にはメタンガスが発生しますが、メタンガスには二酸化炭素の約25倍の温室効果があります。食品ロスを減らすことは温室効果ガスの発生を減らすことになり、地球温暖化の防止につながります。
飢餓問題と未来の食糧不足
現在世界では、人口の9人に1人が飢餓に苦しんでいます。2050年には世界の人口が97億人にまで増加すると予測されています。日本では少子化が問題視されていますが、世界的に見ると大幅な人口増加が予測されています。そして、人口増加においてもっとも危惧されているのが「食糧不足」です。2050年時点で現在の1.7倍の食糧が必要になる一方で、温暖化により食糧生産が減り、世界的な食糧不足が起こることが予測されています。
税金の無駄遣いと経済損失
自治体が一般廃棄物の処理に要する経費は年間 2 兆円にも上りますが、一般廃棄物の半分近くは食品由来の廃棄物と言われ、 食品ロスを処分するために多額の税金が使われていることになります。

【公務員試験の最新時事】食品ロス削減に向けた取組
現状の食品ロス問題に関して、国、企業、個人されぞれに対し取組が必要とされています。ここでは、それぞれの取組をみていきましょう。
政府の取組
消費者庁は、お店の商品棚で「⼿前」にある商品を選ぶ「てまえどり」や、賞味期限の表示は「おいしいめやす」など、食品ロス削減のための情報を、地域のスーパーマーケットのポ
スターや、川柳の募集、SNS等を活用して家庭レベルでの食品ロス削減を啓発しています。
企業に求められる取組
食品ロスのうち、約半分を占めているのが、事業系食品ロスです。そこで、生産過程で生じる規格外品については、缶づめの加工し、安価での販売を促進する必要があります。
個人に求められる取組
食品ロスのうち、約半分を占めているのが、家庭系食品ロスです。そして、家庭での食品
ロスの主な原因は、料理を作りすぎによる「食べ残し」、野菜の食べられるところまで切っ
て捨ててしまう「過剰除去」、未開封のまま捨ててしまう「直接廃棄」です。そこで、各
家庭で、食材を無駄なく使うことや、計画的な買い物を意識する必要があります。
【食品ロス】出題ポイントまとめ
- 食品ロスとは、本来食べられるのに捨てられてしまう食品のことです。
- 日本での食品ロスの量は減少傾向で、2020年度は年間522万トン(推計値)です。具体的には、1人が毎日お茶碗1杯程度のご飯を捨てているのと同様です。
- 令和3年度の日本における食料自給率は38%で低い値となっていますが、多くの食品をロスしています。
- 食品ロスには、地球温暖化と環境破壊、飢餓問題と未来の食糧不足、税金の無駄遣いと経済損失などの問題があります。
【食品ロス】過去の出題例
【食品ロス】最新時事の予想問題はこちら
アプリ紹介
【食品ロス】Youtubeで時事対策
ライトのYoutube紹介
【食品ロス】参考書はコレで決まり!
ライトの時事書籍
![公務員のライト[試験情報データベース]](https://senseikoumuin.com/wp-content/uploads/2022/12/cropped-logo-color-2.png)